
村上靖彦 × 井部俊子
特別対談
なぜ看護に“教養”が必要なのか
dialogue

◉ 村上靖彦(むらかみ・やすひこ)
大阪大学大学院人間科学研究科 教授
2000年パリ第7大学にて基礎精神病理学・精神分析学博士号取得、東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位修得退学。日本大学准教授を経て08年より現職。『治療の現象学』(講談社)、『摘便とお花見:看護の語りの現象学』(医学書院)、『障害受容からの自由』(シービーアール)、『仙人と妄想デートする:看護の現象学と自由の哲学』(人文書院:近刊)ほか著書多数。
★お知らせ(5/11):村上先生の最新著書『仙人と妄想デートする:看護の現象学と自由の哲学』(人文書院)が5/10に刊行されました。

◉ 井部俊子(いべ・としこ)
聖路加国際大学大学院看護学研究科 特任教授
日本看護協会出版会 社長
1969年聖路加看護大学卒業。聖路加国際病院勤務を経て87年より日本赤十字看護大学講師。聖路加国際病院に復帰し看護部長・副院長を務める。2003年より聖路加看護大学教授、04年より16年3月まで学長。14年より株式会社日本看護協会出版会社長。『看護という仕事』(日本看護協会出版会)、『マネジメントの探究』『プリセプターシップ』(ライフサポート社)、『専門看護師の思考と実践』(医学書院)ほか著書多数。
看護は “医療” でなくなる時に
看護になる
井部 村上さんが『摘便とお花見』(医学書院)を出版された時に行った対談で、次のような言葉が印象に残っています。▶ 対談:解きほどかれる看護師の語り(週刊医学界新聞, 第3048号, 2013年10月21日)
「“こんがらがった”看護の日常は、現象学を実現できる題材として非常に魅力的だし、解き明かしたい謎に満ちている」(村上)
「一見ありふれた日常と地続きのような看護に、実は深い意味があることをどう言語化、あるいは概念化していくか、これは大きな課題です」(井部)
今日はこの続きを議論したいと思います。
村上 看護師さんがいる現場はどこを切り取っても、考える材料がたくさんあります。哲学にかぎらず心理学や社会学、教育学などほとんどすべての学問にとっても興味深い、複雑かつ幅の広い世界なのです。それは看護師さん側からすれば、普段何気なく行う実践の中にたくさんの「考える種」があって、その思索にいろんな学問領域が役に立つということですね。
井部 でも看護師たちは、そうは思っていない。患者や家族から感謝され、いくらか自分を立て直してまた明日の仕事に向かうことはあるにしても、自分たちの経験から「自家発電」ができていない。村上さんのような人が常に周りにいて「そこは面白いね」と言ってもらわないと、なかなかその意味を見出せないのかと思います。
村上 もしかすると、看護の面白い部分、大事な部分が見えにくいからかもしれません。看護師さんは、働く上でのルールが大変厳しい中でも、自発的に「隙間」をつくっておられますよね。そこでちょっとした工夫をしたり、患者さんや家族の調整をしたり。特にエキスパートの方は自発的かつ自由に、ある意味「自家発電」をされているなと思います。しかもそれは、何かの学問領域に乗っかるような作業ではないところが面白い。
井部 「隙間」というのはとても魅力的ですね。でもそのような言葉をつけられるのは、やはり村上さんのような特別な作法を身につけた人たちなのです。
村上 どうでしょうか。たとえ言葉を与えなくても、看護師さんたちは実際にそれをやっておられますし、その中で自己実現されていると思います。仮に言葉を与えることが必要だとしたら、それは“教養”やリベラルアーツといったものが看護にどう関係するのかを確かめる、1つのきっかけかもしれないですね。
井部 社会学者の吉田民人さんが「看護学は文科系でもなければ理科系でもない。それらを融合した新たなジャンルの学問だ」というようなことをおっしゃったことがありました(日本看護系学会協議会ニュースレター, 2002)。文理の融合だからこそ言語化する力もまだ十分開発されておらず、学問が体系として確立されていない。
村上 医療の言葉で語られていながら、でも実はちょっとそこではないところに看護というものがあるのではないでしょうか。それがまだ言葉になっていないからこそ、僕らには考えたいことがたくさんあり非常に魅力的なのです。僕と付き合いのある多くの看護師さんが「看護は医療ではない」とか「医療でなくなる時に看護になる」とおっしゃいますが、全くそのとおりだと思います。
看取りのケアは「楽しい」?
村上 僕は今は訪問看護ステーションでフィールドワークをしているのですが、訪問に出る看護師さんは生き生きとしていますね。患者さんの生活と看取りをどうサポートしていくかという視点なので、以前に病院の看護師さんたちから聞いたお話と全く違うし、見ていても違います。
井部 村上さんはそこで、どのように佇んでいるのですか?
村上 慢性期で状態が安定している患者さんのケアに一緒について、たまにシーツを持ったりもしています。ここまでに5人の訪問看護師からインタビューを取ったのですが、そのうちの1件をもとに書いた原稿を発表したらクレームが来たんです。ある訪問看護ステーションの所長さんから「私たちはそんな看護はしていません!」というお怒りのメールをいただいてしまった。でもむしろ幸運なことだと思ってインタビューをお願いし、その方が5人目になったのです(笑)。
井部「そんな看護はしていません!」ってどういう内容ですか?
村上 20年の病棟経験があり、最近在宅に移られた看護師さんで「在宅での看取りは本当に楽しい」とか「医療者にとっても、患者さんやご家族にとっても楽しい経験」というふうに「楽しい」という言葉を何回か使われました。これに対してその方は「私はよかったと思ったことも楽しいと思ったことも一度もない。いつもずっと悩み続けて、逡巡しながらの毎日です」という長いメールを送ってくださったわけです。
井部 よほどそのことを訴えたかったのですね。
村上 でもそのおかげで、すごくいいインタビューが取れました。「楽しい」という言葉があった訪問看護ステーションの看取りは高齢者が多く、メールをくれた方のほうでは若年のがんと神経難病の方をたくさん看ておられたのです。経験されてきた内容が大きく違う。後者のインタビューでは、お子さんを残していく若いお母さんたちに付き添う経験が多かったから、当然それは「楽しい」とか「よかった」という経験ではないですよね。
井部 よくわかります。看護師の立場からすると私たちは病気や人の死について「楽しい」とか「面白い」などと言ってはならないような、強い規範に縛られているように思います。現場では感激したり、大笑いしたくなるようなユーモアを感じる場面もあるのですが、普通はそれに気づいてはいけないという自己抑制がかなり強く働きます。「普通」じゃない人たちは「看取りは楽しい」って突き抜けることができるのですが、経験を積んでいないとそれができず、自分自身を苦しめます。
言葉を与える〜概念化の能力について
井部 週刊医学界新聞(医学書院)の連載「看護のアジェンダ」に「人が患者になるとき、患者が人になるとき」という文章を書きました。▶ 看護のアジェンダ 第131回(週刊医学界新聞, 第3151号, 2015年11月23日)私たちは患者のセルフケアと言いながら、患者自身の能力を奪い取り、意思決定や自分でできることも遮り、すべて看護師が引き取ってやってしまうという状況がここに描かれています。セルフケアや自律あるいは尊厳という概念がいったいどういうことなのか、現象と概念化の往復がまだまだ不十分で、それを現場で落とし込めていない看護師の弱みを露呈したかったのです。
村上 患者さんは、医療の勉強をすることによって患者として自立していくということですか?
井部 知識を持つことでエンパワーされる。つまり、患者から人に戻るんです。この看護師は患者に知識を与えない、もしくは十分に与えるだけのものを持っていなかった。質問されて答えるのは医師や薬剤師で、私はそこにも忸怩たる思いがあります。看護師が行うケアの中に人間の権利を剥奪している要素が含まれているんだなと、しみじみ考えさせられました。自分たちはそれに気づかず、そのことで忙しさを倍増させているのです。
村上 やはり「言葉を与える」ということが、先生の大きなテーマになっているのですか?
井部 私たちは概念化の能力を身につけ、強化することを模索しているのですが、まだその方法論を見つけていません。村上さんが言う「言葉を与える」、つまり「それはこういうことですね」と言葉を置き換えて説明することができると、もっと楽になるかもしれません。
村上 自分が直面している状況に応答する。あるいは状況をしっかりと理解する。そのための言葉を残すことが重要なのですね。たとえば専門看護師の方たちはその訓練をものすごく積まれますよね。一般の看護教育の中にもうそういった言葉にするプロセスは組み込まれてはいるのでしょうか?
井部 専門看護師のそうした能力は、大学院で文献を読み、ディスカッションして書くことで磨かれます。私はそのような修士レベルでなければ、看護の現象を概念化して語ることはできないのではないかと、最近思います。しかし150万人の看護職全員がそうした機会を持つことはできない。
村上 でも一方で、たとえば先ほどの「看取りが楽しい」とおっしゃった方などはごく普通の看護師さんですよね。ベテランで20年間続けられるような方たちは、語り自体はぐちゃぐちゃだったり、繰り返しが多かったりもするのですが、その中に「種」はすでに埋まっている。ある意味でそれは、すでに皆さんできているのでは?
井部 私の取り越し苦労なんでしょうか。
村上 今回、教養についてお話をすることになり、僕にとって看護って何だろうって考えてみました。それは自分が少年だった頃に読んでいた文学と同じだと思ったんです。思春期にたくさんの小説を乱読しながら僕が考えようとしていたことと同じような経験を、看護師さんもされているんですよ。考えるための材料が看護師さんの言葉の中にいっぱい詰まっている。だから、すでに持っている力を発見する必要があるのかもしれません。
井部 パトリシア・ベナーは、埋もれている知識を発掘することは研究者がやるべき重要な役割である。しかし看護学はそれを怠ってきたと言っています。実際にはいろいろな人が掘り起こす作業に手をつけていますが、まだ全体をきちんと体系化するところまでには至っていない。
ケアの背景となる知識体系を
「隙間」で育む
井部 朝日新聞の連載「福岡伸一の動的平衡」で、福岡さんがわかりやすい文章を書く上で心がけているのは、「とはもの」を使わないことだと書いています。例えば「DNAとは」と語り始めた時に、その人はDNAについて熟知した者として上から目線の啓蒙的口調になってしまう。だから「“とは”という言葉の前にある述語や概念に、人間が到達したプロセスこそが、時間軸に沿って丁寧に語られなければならない」と。▶ 福岡伸一の動的平衡 10(朝日新聞, 2016年2月4日)しかし看護師の思考は、プロセスを丁寧に語るがゆえに、それにとらわれて術語や概念に行き着かないかと考えました。
村上 おそらくプロセスを丁寧に語るのはよいことなのではないでしょうか。難しいのは語っていった結果、自分の実践をぴったり表現できる言葉を見つけ出すことなのかもしれません。新しい言葉を見つけるために、幅広い分野の教養が活きると思います。これは看護の問題だけではありませんね。いろんな場所で、自分の専門しか勉強しなくなっているという問題があります。専門外のことにアンテナを張る余裕を社会が失っている。そんな中で、言葉が豊かで幅広いジャンルを吸収されている方もおられるのですが、それを皆に勧めるというのも話が違いそうです。
井部 そうですね。その人たちは現場との間に断絶があると思います。例えば私が今すぐ病棟に立って看護師をやれと言われても、きっとできないでしょう。細かい技術や患者の病態生理、治療法も常に変化しているから。でもそれは一定の期間勉強すれば大丈夫かもしれない。それよりも「隙間」で長く生活していると、そうでない場所で規定された仕事を「いちに、いちに」とやることの不自由さを思い出し、チームの一員として行うことの負担をすぐにイメージしてしまうのです。
村上 先生はいろんな書物にコメントを出されていますが、患者さんと向き合うミクロな次元から、医師や家族あるいは制度、法律などマクロなところをすべて視野に入れてコメントされています。『専門看護師の思考と実践』(医学書院)もそうでした。患者さんの症状というピンポイントから、逆にすごく引いたところまで、看護師がどんな介入を実践したかを記されています。
井部 一人ひとりの専門看護師が述べた内容をどう総括するかという視点で書きます。そういう指摘で触発されるんですが、格好よく言えばこの作業は私の1つの知的な到達点ですね。
印象的な事例の一つに、患者の主治医を変えたCNSがいました。それは専門看護師が決断した最良の方策だったわけです。患者は社会的に活躍している40代の方で、病名の認知や治療法の選択、身体変化への対処など自律して行える人でした。病状の進行に伴いそれらが困難となって家族の支援が必要になりましたが、父母と弟は突きつけられた現実に大きな戸惑いを感じてしまいます。
そんな状況にある家族システムの安定を脅かしたのが、信頼できない主治医の存在だったのです。専門看護師はさまざまな状況から判断して医師の交代が必要と決めました。結果として家族に安定がもたらされ、家族が主治医に向けていた負のエネルギーを患者のケアに変換することができました。
私は次のように書いています。「専門看護師が主治医への配慮を示しながら主治医の交代を迫る場面は圧巻である」と。つまり、病院の中で主治医を変えるなんて誰もできないと思っていますが、この専門看護師は、それを極めて普通にやったわけです。
村上 これからは、どの看護師もそのようになっていくべきなのですか?
井部 本当に看護師がアドボケイターだと言うのなら、患者にとって最善のことを普通にできなければならないでしょう。まず、病棟師長がこのような力を持つといいと思います。
「すぐに役立たない」が
「じわーと効いてくること」
井部 朝日新聞の連載「折々のことば」で鷲田清一さんが、中勘助の『銀の匙』を3年かけて読む授業を続けた教師・橋本武さんの言葉、「すぐに役立つことは、すぐ役立たなくなる」が取り上げられていました。▶ 折々のことば(朝日新聞, 2016年2月5日)
看護師は薬の効能と副作用も学ばなければいけませんし、この治療はどのような病態生理のもとに行われているのか、体位交換する時にどんな技術を使ったらいいのかなど、たくさんのノウハウを学ぶことで精一杯です。それ以外の「すぐに役立たない」ことについては後回しにせざるを得ない。大学院では自分の研究に活かすために現象学や哲学などを一所懸命に学びますが、実践家にとってそれらは二の次です。でも歳を取ってみるとそういう知識こそが「じわー」と効いてくると、私は思うのです。
村上 すぐに役に立たない知識というのは、経験の蓄積に裏打ちされたときに活きてくるかもしれませんし、直接はまだどこにも書かれていないのかもしれません。それは先ほどの「医療でない部分の看護」に多いと思うし、本を読めば学べるといった話ではないですよね。
井部 知識だけでなく経験をブレンドすることが大切です。「すぐに役立たない」が「じわーと効いてくること」をどのようにして吸収するかですね。
村上 どこで見つければいいのでしょう?「じわーと効いてくること」を。
井部 それは、最初に戻りますけど「自家発電」することだと思います。その力を高めるために教養があるのではないかと思います。
村上 つまり教養とは、自分自身の実践に意味を与えられるように、思考するための「何か」を手に入れることなんですね。冒頭の「一見ありふれた日常と地続きのような看護に、実は深い意味があることをどう言語化・概念化していくか」という言葉に結びつきます。
井部 言い換えれば、この大きな課題を解く一つの手がかりとして、教養を吸収していくということではないでしょうか。
村上 それは何かをやみくもに勉強することではなく、どちらかと言えば、それぞれの看護師さんたちの実践の中から「問い」を見つけるような作業ではないかと思います。僕の知る実践研究をされている方々の「問い」は、必ず医療的な知識の外側にあります。
井部 それを見つけるには、経験するという時間が必要なのかもしれません。だけど少しでも早く「看取りが楽しい」と言えるような境地に行けたら、もっと楽になれるんじゃないかと思うんです。
村上 きっかけも大事ですね。『摘便とお花見』(医学書院)の事例でも、小児がん病棟のGさんは子どもの看取りを経験したことが大きかったし、訪問看護師のFさんの場合、最初にお勤めだった小児科の病棟で同僚の看護にショックを受けたことがきっかけになっています。その瞬間にはネガティブな経験だったとしても、気づきや学びのきっかけとして人が成長するチャンスとなり、「問い」を発見し教養を吸収していくことにつながるのだなと思います。
井部 タクシーの運転手から聞いた話ですが、地方で医学会が開かれると、医師たちは会場で登録を済ませてそのまま観光に行く人が多いそうです。看護師の学会ではみんなずっと真面目に演題を聞いている。私はもっといろいろな所に出かけていくような看護師が増えるといいなと思っているんです。教養とはそういう緩やかなものではないでしょうか。シリーズ「教養と看護」も、今の看護師たちにもっと励めと負荷を与えるのではなく、仕事を楽にする栄養剤のようなものになってほしいですね。
(2016年2月19日 日本看護協会出版会にて)
★この対談の縮小版を、まもなく発売の月刊「看護」5月号に掲載しています。
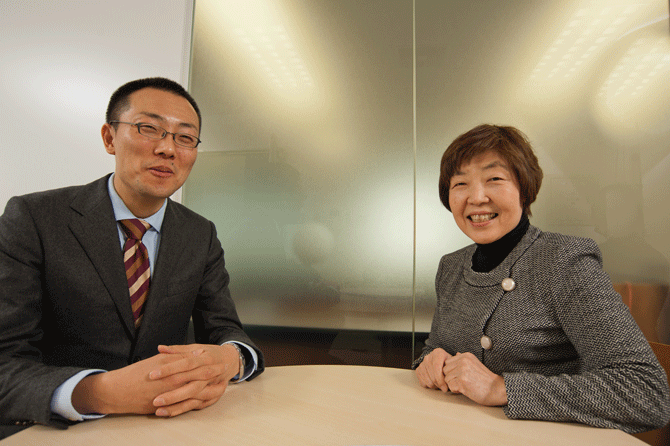
写真(人物):坂元 永
コメント: