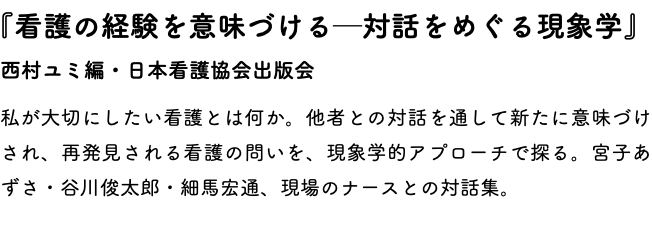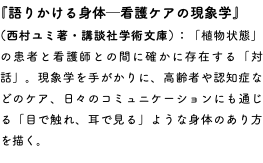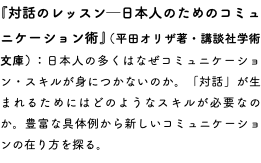●4:演劇情動療法
認知症患者の非薬物療法の1つ。東北大学医学部の藤井昌彦医師らが中心となって開発した世界初の情動療法。患者の残された情動機能を刺激することでBPSDを抑制し、日常生活を活性化させるなどの効果がある。
●5:コンテンポラリーダンス
既成のジャンルに属さない自由な身体表現。
< ● ●
認知症患者の喜びを引き出す「演劇情動療法」
西村:今のお話を聞いて、こまばアゴラ劇場については、日常とは少し違う印象を受けました。劇場の中はかなり狭く、一度座ったら立ち上がれない。まさに拘束状態であり、そしていつ始まったかわからないうちに、もう演劇が始まっている。さらに、演じる役者さんたちの動きがワンテンポ速かったり、遅かったりするんですね。
それに、声のトーンが高かったり、自分と比べて随分ずれている感じがして、あのずれ感によって、今思えば「知らない間に始まったと感じるのは、私はいつもは準備された状態で物事を始めているんだろうな」とか、「私はそういう間(ま)で生きていないな」「私はそういうトーンでしゃべっていないな」など、いつもの自分というもののあり方を気づかせるような機能が、この演劇にはあるんだろうなと思いました。
平田:演劇もダンスもそうですが、私たちが観ている人に味わってもらいたいことというのは、本来は身体の面白さや違和感なんですが、一方で私たちは近代人なので、ストーリーやテーマを追ってしまうんですね。なのでその部分を外すことで、結構そういう面白さが出てくるんです。
最近、認知症の治療や予防に演劇がすごく取り入れられているんです。東北大学の藤井昌彦先生が演劇情動療法●4を提唱なさって、俳優が介護の訓練を受けて現場に入っていったり、介護の専門家が演劇のワークショップを受けて実践したりしています。人間の脳には大脳辺縁系というものがあり、これが情動・感情を司っている。その周りには新皮質があって計算や記憶を司っている。この新皮質が弱ってくると、認知症になるといわれているんですね。
最近の大脳生理学の流行りでは、新皮質の機能が低下していても、大脳辺縁系のほうは弱っていないんじゃないか、逆に脳には弱った部分を別の部分が補う機能があるから、むしろ大脳辺縁系は活性化しているんじゃないか、だから認知症の人は怒りっぽいし、同じくらい喜ぶ力も強くなっているんじゃないか、という考え方が注目されているんです。
例えば、認知症のおばあちゃんがお財布を開けて「1万円札がない。あんた盗んだでしょう!」と言われたら、「いえ、盗んでません。おばあちゃん、どこかに忘れたんじゃないの?」というふうに、これまでは新皮質に訴えてきた。つまり論理で説明していた。でもそうすると「あんたが絶対に盗んだんだ!」ってまた怒っちゃうわけです。
こんなとき、演劇情動療法ではどうするかというと、支援者は「俳優」なので、一緒に驚いてあげるんです。「えっ? ないの! 大変! え〜っ⁉ 1万円札なかったら大変じゃん! 俺のバイト代だよ〜」みたいな感じで(笑)自分も探すんですよ。おばあちゃんと一緒に、もう部屋中をかき回して10分でも20分でも探すわけ。
そうするとだんだん疲れてくるでしょう? 「ないねえ、どうしよう……。じゃあお茶でも飲もうか? よし、俺、お茶飲んだらもう1回探すからね」って言って、お茶を飲み終わる頃にはもう、ほぼ忘れている。それでこの話はおしまい(笑)。
こうすれば、どっちにもストレスがたまらない。在宅看護に携わるような方に、こうした訓練を受けてもらうといいんですね。ご承知のように、認知症の方への投薬の半分くらいが精神安定系の薬が占めているので、藤井先生が勤めている仙台富沢病院で実際に全面的に取り入れてみたところ、薬の量が劇的に減ったというエビデンスも得られました。
認知症の診断では「100ひく13」っていう計算を30問させて「10問ダメだったら危ない。15問だと認知症。20問だと重度」といった判定がされるんですが、藤井先生は「人間は、そもそも“100ひく13”に即答できる必要があるのか?」と主張されるんですね(笑)。「近代以前の農民は、そんなこと聞かれれても答えられなかっただろう」と。つまり、私たちは近代人だから「100ひく13」に即答できることを前提にして、この複雑な社会を構成しているんですよね。だから小学校1年生になると、九九を徹底的に覚えさせられる。できないと困るから。
だけど、病院や介護施設のような生活の場であれば、それでよしとしちゃえば、かれらに暗算は必要ないんですよ。それでね、暗算する必要がないとなれば、認知症の患者さんたちは、みんな電卓を使い始めるらしいんです。電卓は使えるんですよ。結果的に「できないこと」より「できること」が増え、どんどん薬の量が減っていくんです。
ここで先ほどの話に戻るのですが、認知症の方たちに観せると最も受けるのがコンテンポラリーダンス●5なんです。反対にボランティアの方がやる盆踊りなどが一番評判悪い。最前列の人はわ〜って楽しんでいるけど、3列目くらいになると「へたくそだなあ」とかって言ってて(笑)、認知症の人は容赦なかったりするからね。
私たちは普通、ストーリーとかテーマとか、どうしても新皮質で演劇を鑑賞しちゃうんですね。どんなにヘンな作品でも「この作者の意図は?」みたいに考えちゃうんだけれども、認知症の人には人間の身体の動きの面白さだとか、言葉の変さ、言葉の音とかに反応して観る傾向がある。だから、まさにそれらを楽しめるコンテンポラリーダンスが受けて、それも一流のものにしか反応しないということがわかったんですよ。
西村:厳しいですねえ(笑)。
平田:なので、アーティストの審査は、これから全部認知症の人にやってもらおうかと(笑)。
西村:いいと思います(笑)。認知症の方に限らず、素晴らしいものには理屈ではなく身体が惹きつけられたり、思わず踊ってしまったりするような力がありますよね。
平田:そういう力を応用したダンスセラピーも流行っていますね。
「キャラ変」ではなくて「キャラ増」
西村:われわれ医療職でも、白衣を着るとテンションが変わる人って結構いて、それはつまり、特に患者さんの前では専門職としての自分の役割みたいなものを「演じて」いると思うんですね。そうするとつい相手に対して「もっとこうしないといけません」と、指導モードになってしまう。先ほどのような、認知症の患者さんと一緒に1万円を探すようなトーンに持っていくには、どうしたらいいのでしょう?
平田:演劇をやるんですよ(笑)。まずは、演劇をやる。
西村:いつもの役割演技ではなく、演劇をやる?
平田:まず前段として「演じることは楽しい」ということに気がついてもらわないといけないんです。こういう話を学校などで話すと、まじめな高校生が「じゃあ、嘘をつけってことですか?」って言うけど(笑)、そうじゃなくて「担任の先生に聞いてごらん。先生として教壇に立っている時の態度と、家に帰って自分の子どもといる時の態度が、『俺、ぶれない男だから』とか言って同じにしていたら、そりゃ相当社会性のない人だよ」って(笑)。「先生にとって、君たちに対する態度と、お子さんに対する態度は違うもの。でもそれぞれを真剣にやっているんだよ。嘘をついているわけじゃないでしょう?」「それが大人になるってことなんだよ」って言うんですけどね……。今の子たちはほんとに真面目なので大変ですよ(笑)。
西村:大変ですね(笑)。
平田:だから、折れてしまいやすいんでしょう。
西村:簡単に折れないためには、もう少し演じることが普通にできたらいいのかしら。でも、彼らも学校では学校での自分を演じているって言われますよね?
平田:いわゆる「ペルソナ(persona)」ですが、これはパーソン(person)の語源となった「人格」のほかに、「仮面」という意味も兼ね備えています。人はいくつもの仮面をかぶり分けることで、社会のさまざまな場に適応できているわけですけど、今の子どもたちは学校で過ごす時間が長いせいで、ずっと同じ仮面で過ごさなければいけない。
でも昔は学校だけでなく『ドラえもん』に出てくるような原っぱがあって、家に帰れば兄弟姉妹も何人かいた。クラスで同世代と無邪気に遊ぶ自分、原っぱに行ってお上級生に甘える自分、家に帰ると弟妹がいるからしっかりしなきゃいけない自分など、そうしたいろんなキャラクターを行ったり来たりすることによって、おそらく人格というものが形成されていたんでしょう。
最近、若い人に聞いたんですが、以前から「高校デビュー」「大学デビュー」という言い方があるんですね。中学までのいじめられっ子が、誰も自分を知っている人がいない高校に行って、そこでかっこいい自分になるっていう、ワンチャンスを狙うんですよ。
西村:それは危険ですね。
平田:うん、危険なの(笑)。失敗すると悲惨なことになるんだけど。で、最近はそれを「キャラ変」って言うらしいんです。キャラクターを変える。
西村:キャラ変! わざわざ?
平田:そう。キャラを変えるたび、新しいキャラクターをつくらなければいけない。「本当の自分があるのに、嘘の自分を演じさせられている」って思うから、それだとつらくなっちゃう。だったら、変えるのではなく、キャラを増やす「キャラ増」のがいいと思うんです。つまり主体的に演じ分けられればいいんです。
大阪大学医学部保健学科看護学専攻の新入生宿泊研修では、僕のワークショプを3時間受けることになっているのですが、その際に「勉強も大変だろうけれども、何か趣味を持ったほうがいいよ」「君たちの人生は看護師の時間だけではないし、ほかの時間がその看護師の時間を支えるのだから、大学の4年間にいろんなサークルに属したりして、一生の友だちとか生涯続けられるような趣味を見つけたほうがいいよ」って必ず言うんです。
西村:それは大切ですね。
平田:ほかにも、東邦大学看護学部では、初年次で芸術系科目を10種くらいの中から選択できるようになっていますし、昨年開設された関西医科大学看護学部では、初年次教育にオムニバスでホスピタルアート、音楽療法、ダンスなどの音楽・アート・演劇のアーティストによる授業(表現とコミュニケーション)を組み入れています。今後はそういう大学がたくさん出てくると思います。
アクティブラーニング化と等質性
西村:例えば、授業の中に演劇を組み入れるとして、4年生くらいになると人前でパフォーマンスをする力も随分とついてくるのですが、学年が低い学生同士、いつものメンバーの前で、いつもと違うことをするのはすごくストレスだと思うのです。何か工夫がいるのかなと思うのですが……。
平田:慣れもあるので、そもそも演劇を小中高でやっていれば、そんなに大変じゃないんです。例えば音楽と美術は学校の科目にあるのだから、同じ表現行為でも、恥ずかしいから笛は吹かないとか、絵を描かないという子はあまりいないでしょう。僕にとっては演劇よりもむしろ笛を吹くほうが恥ずかしい(笑)。でもみんな当たり前にやっている。もともと科目にあるからです。
ちなみに先進国では、少なくとも高校の選択必修科目に演劇があるんですね。皆さんの選択肢は音楽と美術と書道だったでしょう? 美術のない国は結構あるんですが、普通は音楽と美術と演劇なんですね。
西村:これから演劇を加えてはダメですか?
平田:今、演劇教育を入れるというのは大変なんですよ。小学校からプログラミングも英語もやらなきゃいけないし、教育では限られた資源を取り合わないといけないからで。それでいきなり大学生から演劇をやらせるのは難しい、ということが1つ。ちなみに韓国では4年ほど前、すべての高校の選択必修科目に演劇を入れました。台湾もシンガポールも似たような政策があるので、日本はアジアの先進国の中でも遅れをとってしまっています。
あと「等質性」の問題ですが、今はどの大学でも「アクティブラーニング●6化」が進んでいます。例えば東京工業大学は初年次教育を最もきちんとやっていて、ジャーナリストの池上彰さんが中心となり、20人・1クラスで立派な文系の先生を担任につけて、毎週読書会を開いています。僕も毎週呼ばれる講座があり、そこではディスカッションもやります。
でも東京工業大学はいま「876問題」と呼ばれる大きな困難を抱えています。学生の8割以上が男子で──看護の逆ですね──、7割が関東出身。すごくいい大学なんだけれど、関西での知名度が本当に低い。そして6割が中高一貫校の出身なので、ディスカッションをさせても皆似たような意見になってしまう。
西村:なるほど。
平田:アメリカの大学では、従来型の学力試験で採る学生は上位2割といわれています。アメリカの面白いところは、ハーバードやプリンストンなどは、下位2割の学生を寄付金の額で採るんです。もちろん最低限の学力はある上でですよ。額は1億円とか、2億円とかで、1人1億円だとすると100人だと100億円でしょう?
でも、どうしてそれが社会的に許されるかというと、そのお金を基金にして、経済的に困難な家庭の学生を生活費まで面倒をみて入学させるんです。要するに、すべての授業がアクティブラーニング化していてディスカッションが中心だから、富裕層も、中間層も、貧乏な人もいなければいけないし、地域、宗教、LGBTを含む性別、いろんな人にいてもらわないといけない。
これらの大学では、もともと試験システム自体が多様性を見るものなんですね。日本での2020年の大学入試改革の肝もそこにあるのですが、今そういう話を講談社の『本』という雑誌で連載していて、来年新書で出ますので、ぜひ買ってください(笑)。それはともかく、等質性の問題はどこでも抱えていますが、特に看護は大変ですよね。
西村:はい、ほぼ女性ですし、もともと他人に関心がある人が多い。私、大阪大学に行って一番衝撃を受けたのは、ある同僚に「どうして西村さんは、他人のことばかり調査して、他人のことばかり書いて、自分のことを書かないんですか」と聞かれたことでした。「自分のことは調査者だと思っているから、調査をするのは私、調査対象がどこかにあると思って見ているのです。それをどう見るかは私ですけれども」と言ったら、「いや、僕たちは他人よりも自分に関心があって、まず自分をもとに考え始める」と言うんです。
でも、私の周りの人はみんなそうです。これも看護職の傾向でしょうか。大阪大学はすごく楽しかったのですが、同時にすごく疲れていたなって、今の看護系大学に戻ったときに実感しました。以前よりも忙しいんですが、ほっとしたんです。でも、この同質の中に居続けるという状況は、長い目で見るとよくないかもしれません。もっと異質なものに開かれていなくては。
人生に迷ったときに効く、リベラルアーツ
平田:もちろん同質性のほうが居心地はよいのですが、でも日本社会も看護の世界もそうはいっていられないですよね。ここは、大学の教員としては考える上でポイントがいろいろとあって、確かにアメリカみたいに初年次を全部リベラルアーツ●7にしてしまうというのも1つの手だとは思うのですが、看護の場合は基礎的に学ばなければいけないことがあまりにも多いから、そうもいかずなかなか難しい。
私たちがいたコミュニケーションデザイン・センターは、もともと大学院の高度教養教育ということで、鷲田清一さんが副学長になるときに、「大学院教育改革をやらせてくれ」と当時の宮原秀夫総長にお願いしたことによって設立された、という経緯があります。それはどういうことかと僕なりに考えて定義づけたのは、要するにリベラルアーツは、人生に迷う、人生を選択する時期に受けると一番効くということです。僕の世代の恩師で戦前の教育を受けている人たちは皆「大事なことは全部旧制高校時代に学んだ」と言うのですが、要するに文理融合で同じ釜の飯を食っていた。まさにリベラルアーツを学んでいたんです。
今、例えば大阪大学の場合、理学部の9割、工学部の8割の学生が大学院に行くんです。世の中では「大学全入時代」と言っていますが、私たちにとっては「大学院全入時代」なんですね。そんな彼らが人生に迷うのは修士1年生のときで、大学院に残るか就職するかを考えるわけです。だって8〜9割が大学院に行くんだから。ところが日本の大学院では、教員たちは学生全員が学者になるつもりで教えるんですよ。全員が学者になったら大変なことになっちゃうんですよ。日本が崩壊しちゃうんだけど(笑)、当然自分と同じように研究者になるつもりでしか教えていないから、大学院教育が日本ではまだ確立されていないわけです。
COデザインセンターで授業していても、修士1年生の後期くらいが一番よく授業を聞いてくれるんです。迷っているから。迷っているときに僕みたいな大学教師と出会うと、それで間違って人生を棒に振っちゃったり(笑)……。でも、そういうことが大事だと思うんですね。だから、どのタイミングでやるのがいいのか。「教養の森」って呼んでいるんですけれども、例えば、和歌山大学では1年生から4年生まで、いつでも教養教育を受けられるようにしています。
西村:私にとって教養とは、生きていく上で特別な困難があったとき、今までと同じテンポでものを考えるのではなく、自分の専門とは違うものに多数触れることによって、生きる力になりうる力を持つものだと思います。学生たちを見ていると、3〜4年生で教養に出会ったほうが将来の彼らのためにもなるのかなと思います。
平田:たしかに、特に看護はそうですよね。
西村:そのほうが、本当の意味での教養を学ぶことになると思うのです。1年生では、おそらくまだそういう理解はしないままなんじゃないかな。
<おわり>
(2019年4月23日・紀伊國屋書店新宿本店にて)
編集協力:石川奈々子
< ● ●
●6:アクティブラーニング
学習者が能動的に学べる授業を行う学習方法の総称。
●7:リベラルアーツ
教養教育。元々はギリシア・ローマ時代の「自由7科(文法、修飾、弁証、算術、幾何、天文、音楽)」を起源とする。